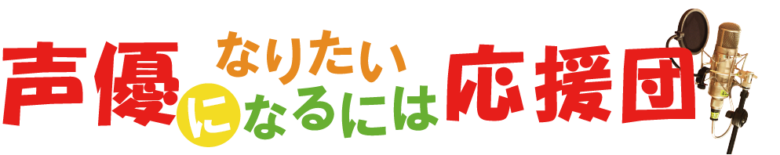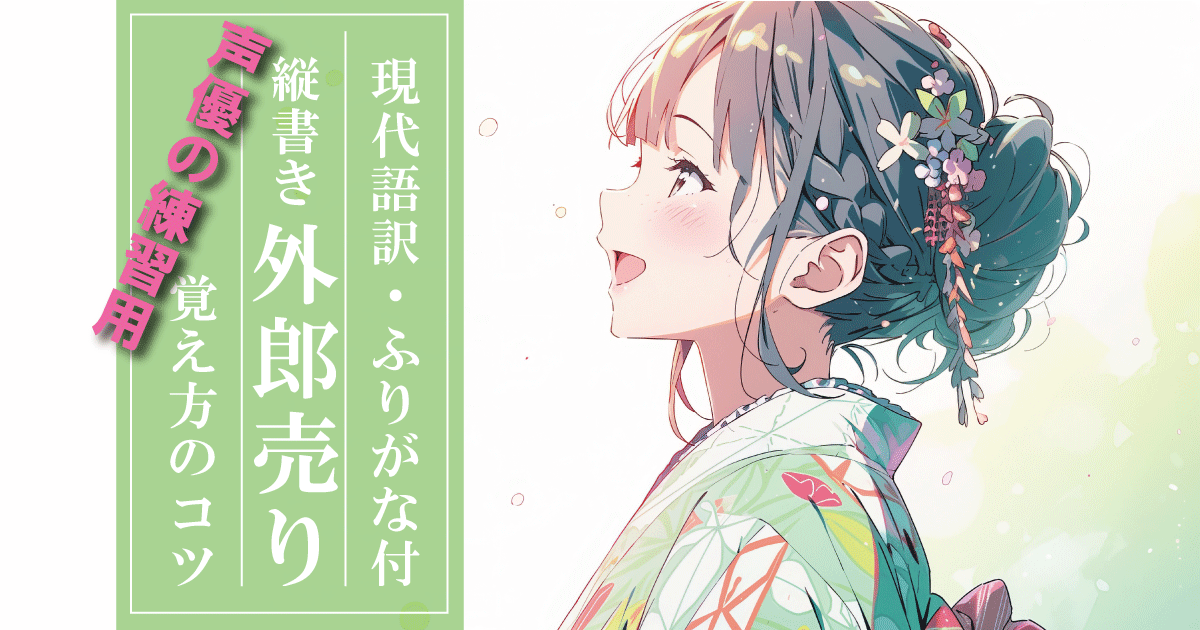声優になるには避けては通れない道、それが「外郎売り」ですよね。
今回はふりがな付きの「外郎売り」の全文と現代語訳
印刷して練習したい方のためにPDFでダウンロードできるようにしました。
覚え方のコツもお教えします。

こんにちわ!現役声優・ナレーター・演劇団体代表の「しいな」です!
名前は明かせないけど、声優を目指す人なら必ず一度は耳にする事務所に所属しています!
外郎売りは、最初びっくりするくらい難しいですが、だんだんと上手くなりますよ。
これから声優スクールや養成所に通う人、これから探すという方は以下↓も読んでみてくださいね。
はじめに
外郎売りは使用するテキスト・教わる方・時期によって読み方や表記に違いがあります。
ここでは私が教わったものを書いてますのでご了承ください。
今後、講師に教わる際にはその方のご指導に従って訓練をするようにしてくださいね。
なお、ここでは文面や現代語訳は横書きで書いていますがダウンロードしたものは縦書きですのでご安心ください。
現代語訳はタップかクリックすると開きます。
早口言葉が始まると「読んだまま・意味のないもの」は省いています。
重ねてご了承ください。
まずダウンロードしたい方は外郎売り全文ダウンロードへどうぞ
ふりがな付き外郎売り全文(現代語訳あり)
外郎売り
拙者親方と申すは、お立会の中に御存じのお方もござりましょうが、
お江戸を発って二十里上方、相州小田原一色町をお過ぎなされて、
青物町を登りへおいでなさるれば、欄干橋虎屋藤衛門、只今は剃髪致して
円斉と名のりまする。
私の店の主は、お集まりの中にはすでに御存知の方もいると思いますが、江戸を出発して近畿地方へ80キロほどの距離。
神奈川県にある小田原の一色町を過ぎ、青物町をさらに進んだ所の欄干橋の虎屋の藤右衛門、現在は髪を剃って円斎と名乗っています。
元朝より大晦日まで、御手に入れまする此の薬は、
昔、ちんの国の唐人外郎という人、わが朝へ来たり。
帝へ参内の折りから此の薬を深く籠め置き、
用ゆる時は一粒ずつ冠の隙間より取り出す。
依ってその名を帝より、透頂香と賜わる。
即ち文字には、頂き透く香いと書いて透頂香と申す。
元日の朝から大晦日まで、手に入れることができるこの薬は、昔に「ちんの国」の「外郎」という人が、帝に会いに来る際、
この薬を大事にしまっており、使う時は一粒づつ冠り物の隙間から取り出していた。
それを見た帝に「透頂香」という名前をつけていただいた。
文字で書くと「頂き」「透く」「香い」という字を書いて「とうちんこう」といいます。
只今はこの薬、殊の外世上に弘まり方々に偽看板を出し、
イヤ小田原の灰俵のさん俵の炭俵のといろいろに申せども、
平仮名をもってういろうと記せしは親方円斉ばかり。
今では思ったよりも世の中に広まっており、色々なところで偽物の看板が出ています。
小田原だとか、灰俵だとか、さん俵だとか、炭俵だとか色々言っているけれども、平仮名で「ういろう」と書くのは私の店の主の円斎だけです。(これだけが本物です)
もしやお立会いの内に熱海か塔の沢へ湯治にお出なさるるか、
又は伊勢御参宮の折からは必ず門違いなされまするな。
お登りならば右の方、お下りなれば左側、
八方が八つ棟、表が三つ棟玉堂造り。
破風には菊に桐の薹の御紋を御赦免あって系図正しき薬でござる。
もしも、皆様の中で熱海か塔ノ沢へ湯治に行ったり、またはお伊勢参りの際には店を間違えないように気を付けてください。
近畿方面へ向かうときは右側で、江戸方面へ向かうときは左側です。
八方が八棟で、正面から見ると三棟の「玉堂造り」、破風には、菊に桐の薹の御紋が付けられた、歴史のある由緒正しい店の薬です。
イヤ最前より家名の自慢ばかり申しても、
ご存知ない方には正身の胡椒の丸呑み白河夜船。
さらば一粒食べかけて、その気味合いをお目に懸けましょう。
先ずこの薬をかように一粒舌の上へのせまして腹内へ納めますると、
イヤどうも言えぬは、胃心肺肝が健やかになりて、
薫風候より来たり口中微涼を生ずるが如し。
魚鳥、茸、麺類の食い合わせ、その外万病速効ある事神の如し。
いや、先程から店の自慢ばかりしても「ういろう」を御存知ない方にとっては、胡椒を丸呑みして辛さが分からない、ぐっすり寝こんで何も分からないのと同じだと思います。
それでは一粒、口に入れて、どんな感じがお見せしましょう。
先ず、この薬を一粒舌の上に乗せて、お腹の中へと飲み込むと、イヤもう、何と言ったらよいか、胃、心臓、肺、肝臓がすっきりして、
爽やかな風が喉から出て来るようで、口の中も涼しくなったように感じます。
魚、鳥、茸、麺類の食い合わせで気持ち悪くなったり、そのほかの病にも神のような速さで効きます。
さてこの薬、第一の奇妙には舌の廻ることが銭独楽が裸足で逃げる。
ひょっと舌が廻り出すと矢も楯も堪らぬじゃ。
そりゃそりゃそらそりゃ、廻って来たわ廻って来るわ。
アワヤ候、サタラナ舌にカ牙サ歯音。
ハマの二つは唇の軽重、開合爽やかに、
アカサタナハマヤラワ、オコソトノホモヨロオ。
さて、この薬の効果の一つは、舌がよく回って、くるくる回る銭独楽も裸足で逃げ出してしまう程です。
ひょっと舌が回り出すと、弓矢だろうが盾だろうが口の回る勢いは止められません。
それそれそれ、舌が回ってきますよ、回って来ました。
『あ、わ、や』は「喉音(こうおん)」「さ、た、ら、な』は「舌音(ぜつおん)」
『か』は「牙音(がおん)」『さ』は「歯音(しおん)」
『は(ファ)・ま』「唇音(しんおん)」二つは唇が軽いか重いか、
口の開け閉めも爽やかで「あかさたなはまやらわ」「おこそとのほもよろを」
一つへぎへぎに、へぎほしはじかみ。
盆豆盆米盆牛蒡。摘蓼、摘豆、摘山椒。
書写山の写僧正。粉米の生噛み粉米の生噛みこん粉米の小生噛み。
繻子緋繻子、繻子繻珍。
親も嘉兵衛、子も嘉兵衛、親嘉兵衛子嘉兵衛、子嘉兵衛親嘉兵衛。
古栗の木の古切口。雨合羽か番合羽か。
貴様の脚絆も皮脚絆、我等が脚絆も皮脚絆。
尻皮袴のしっ綻びを、三針針長にちょと縫うて、縫うてちょとぶん出せ。
河原撫子野石竹。
野良如来野良如来、三野良如来に六野良如来。
一寸先のお小仏にお蹴躓きゃるな。細溝に泥鰌にょろり。
京の生鱈、奈良、生学鰹、ちょと四五貫目。
一つのへぎ(薄くそいだ板で作ったお皿)に、へぎ干し(かき餅)と、はじかみ(生姜)がのっている。
お盆の豆、お盆の米、お盆の牛蒡。摘んだ蓼、豆、山椒。
書写山(寺)の写僧正(お経を写す僧)
粉米(脱穀時に割れて粉になった米)
繻子(絹織物)、緋繻子(紅く染めた絹織物)、繻珍(様々な色を織り込んだ繻子)
脚絆(スネに巻いて保護したり締めることで披露を軽減する)皮製の脚絆
皮袴のほころびを、3針、幅広い縫い目でちょっと縫って、ちょっと外に飛び出せ
京の生の鱈、奈良の生の真魚鰹、4、5貫目(15~18.7キロ)
お茶立ちょ茶立ちょ、ちゃっと立ちょ茶立ちょ、
青竹茶筅でお茶ちゃと立ちゃ。
来るは来るは何が来る、高野の山のおこけら小僧。
狸百匹、箸百膳、天目百杯、棒八百本。
武具馬具、武具馬具、三武具馬具、
合わせて武具馬具、六武具馬具。
菊栗、菊栗、三菊栗、合わせて菊栗六菊栗。
麦ごみ麦ごみ三麦ごみ、合わせて麦ごみ六麦ごみ。
あの長押の長薙刀は誰が長薙刀ぞ。
向こうの胡麻殻は荏の胡麻殻か、真胡麻殻か、
あれこそ本の真胡麻殻。
がらぴいがらぴい風車。
おきゃがれ小法師、おきゃがれ小法師、昨夜もこぼして又こぼした。
お茶を立てろ、茶を立てろ、ちゃっと立てろ、茶を立てろ、青竹の茶筅でお茶をちゃっと立てな。
おこけら=材木の削り屑、木っ端=木っ端のような小僧
天目(天目茶碗ではなく、ただの茶碗)
長押(和室の鴨居のすぐ上に、囲むように取り付けられる化粧板)
むこうにあるゴマをとった後の茎や殻は、荏胡麻のか、普通のゴマのか、あれこそ本当の普通のゴマの胡麻殻だ。
起き上がりこぼし、起きやがれ若い僧、ゆうべも寝小便をしてまた寝小便した。
たあぷぽぽ、たあぷぽぽ、ちりからちりからつったっぽ、
たっぽたっぽ干蛸、落ちたら煮て食お。
煮ても焼いても食われぬ物は、
五徳、鉄弓、金熊童子に、石熊、石持、虎熊、虎鱚。
中にも東寺の羅生門には茨木童子がうで栗五合掴んでお蒸しゃる、
かの頼光の膝元去らず。
鮒、金柑、椎茸、定めて後段な蕎麦切り、素麺、饂飩か、愚鈍な小新発知
干蛸(干した蛸)が落ちてきたら煮て食べよう。
煮ても焼いても食べられないものは、五徳(火鉢に乗せる=ガスレンジの鍋を置く台)
鉄弓(焼き網) 金熊童子(酒呑童子の家来の四天王の一人)石熊(酒呑童子の家来の四天王の一人)
石持(魚=食べられる)虎熊(酒呑童子の家来の四天王の一人)虎きす(魚=食べられる)
酒呑童子の手下の中でも、東寺にある羅生門では茨城童子が(切り落とされた「腕」と「茹で」がかかっている)ゆで栗を五合つかんで蒸している。
かの源頼光の膝元から離れることなく付き従って。
後段な=ご飯のあとにふるまう飲食物のこと
小棚の小下の小桶にこ味噌がこ有るぞ、小杓子こ持ってこ掬ってこ寄せ。
おっと合点だ、心得たんぼの川崎、神奈川、程ヶ谷、戸塚は走って行けば、
灸を摺りむく三里ばかりか藤沢、平塚、大礒がしや小磯の宿を、
七つ起きして早天早々相州小田原透頂香。
川崎、神奈川、保土ヶ谷、戸塚のは走っていけばすぐなので、お灸をして皮がむける三里(膝下のツボの名=三里=距離)くらいに感じる。
藤沢、平塚を通り過ぎて大忙(大磯)しで小磯の宿を午前4時に起きて早朝にきた、相州小田原の透頂香
隠れござらぬ、貴賎群衆の花のお江戸の花ういろう。
あれ、あの花を見てお心をお和らぎゃっという、産子、這子に至るまで、
この外郎の御評判、ご存知ないとは申されまいまいつぶり、
角出せ、棒出せ、ぼうぼう眉に、臼、杵、擂鉢、
ばちばち、ぐゎらぐゎらぐゎらと羽目をはずして今日御出の何も様に、
上げねばならぬ売らねばならぬと息せい引っぱり、
東方世界の薬の元締め薬師如来も照覧あれと、
ホホ敬って、ういろうはいらっしゃりませぬか。
知らない人はいない、身分の高いひとも低いひともみんな、華やかな江戸のように人気のういろうです。
東方浄瑠璃光世界の薬の元締めである薬師如来様もご覧ください、お集まりの皆様も敬って申し上げます。
「ういろう」はいかがですか。
外郎売りなど長いセリフ(科白)の覚え方のコツ!
「外郎売り」や長いセリフの覚え方は長いセリフを覚える4つのコツを読んでみてくださいね。
私が実践している大量のセリフや原稿を覚えるコツが書いてありますよ。

外郎売りを初めて読んだときは「自分の口の回らなさ」にガッカリするかも知れません。
でも最初はみんな同じでいきなりスラスラと読める人はほぼいないと思います。
少しずつ練習すれば、流れるように読めるようになるので頑張ってくださいね!
【読み仮名つき】縦書き外郎売り全文!PDF

台本のセリフも紙がほとんどなので、ダウンロードして印刷してから練習するのがおすすめですよ!
気になるところに書き込んだりも出来ますしね。
🎉 5,000DL突破!ありがとうございます
お役に立てましたら「DL報告」をいただけると励みになります!
Xでは最新の声優オーディション情報なども発信しています。